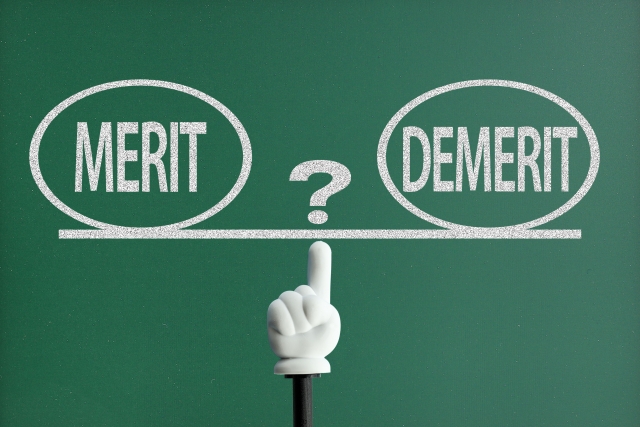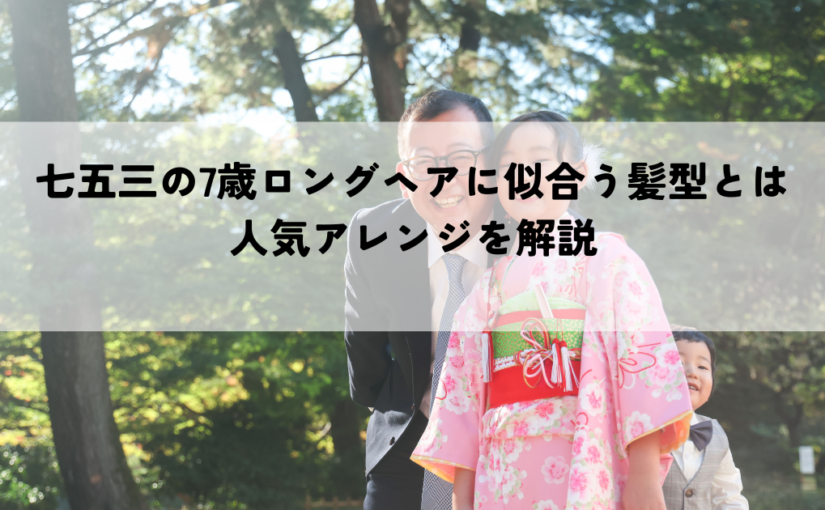七五三の記念撮影は、お子様の成長をお祝いし、家族の大切な思い出を形に残す特別な機会です。
近年は、伝統的な和装だけでなく、洋装での撮影も人気を集めています。
洋装ならではの華やかさや、お子様の自由な魅力を引き出せるのが魅力です。
しかし、いざ撮影となると、どのようなポーズで写真に残せば、お子様の愛情や温かさが伝わるのだろうかと、悩んでしまうことも少なくありません。
お子様と家族の温かさが伝わる、とっておきの1枚を撮るためには、いくつかのポイントがあります。
今回は、七五三の洋装撮影で「映える」ポーズや、成功のためのコツをご紹介します。
七五三洋装撮影で映えるポーズとは
一人写しで可愛いポーズ
お子様一人で写る写真は、その成長した姿をじっくりと捉えることができます。
洋装ならではの可憐さや、みずみずしい表情を引き出すポーズを取り入れてみましょう。
例えば、鏡を覗き込んで身だしなみをチェックするような仕草は、自然な表情を引き出しやすいです。
また、お気に入りの絵本を読んでいるかのように、本を手に持って座るポーズも、落ち着いた可愛らしさを演出できます。
少し遠くを見つめたり、振り返ったりするポーズも、物語を感じさせるような印象的な写真になります。
扉のフレームから顔を覗かせるような、遊び心のあるポーズも「今だけ」の可愛らしさを捉えるのにぴったりです。
家族で楽しむポーズ
七五三の撮影では、家族みんなで写る「家族写真」も大切にしたいものです。
洋装で、家族ならではの温かい雰囲気や絆が伝わるポーズを取り入れてみましょう。
お子様を真ん中にして、皆でぎゅっと抱きしめ合う「ハグ」のポーズは、愛情をダイレクトに表現できます。
パパやママが優しく抱っこしたり、お子様がパパやママの手を握ったりするポーズからは、安心感と仲の良さが伝わってきます。
皆で肩を寄せ合って座ったり、お子様がパパの膝に座ったりする、リラックスした自然なポーズも、笑顔を引き出しやすく、温かい家族の団らんを写し出します。
動きを活かしたポーズ
お子様の元気いっぱいな姿は、写真に躍動感を与え、生き生きとした印象にしてくれます。
洋装の衣装が映えるような、動きのあるポーズもおすすめです。
例えば、床に寝転がって楽しそうに笑っている様子を上から撮影するポーズは、普段見られないような自然な笑顔を見せてくれることがあります。
皆で手をつないで、笑顔で歩き出すようなポーズも、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。
紙吹雪(コンフェッティ)を空に放ったり、それを追いかけたりする瞬間の写真を撮ることで、写真全体が華やかになり、撮影自体も楽しい思い出となるでしょう。

七五三洋装撮影を成功させるポーズのコツとは
子供の自然な表情を引き出す
写真撮影が苦手なお子様でも、リラックスして自然な笑顔を見せてくれるような工夫が大切です。
撮影前にお子様とたくさん話し、どんな写真を撮りたいか、どんなポーズが好きかなどを共有しておくと良いでしょう。
撮影中も、カメラを意識させすぎず、パパやママがお子様に話しかけたり、優しく抱っこしたり、ほっぺをつんつんしたりと、普段通りのスキンシップを試してみてください。
お子様がおもちゃに夢中になっている瞬間や、パパやママに甘えている自然な仕草を捉えることで、生き生きとした表情の写真が撮れます。
成長を記録するポーズを選ぶ
七五三の記念撮影は、お子様の成長を記録する絶好の機会です。
洋装であっても、成長の過程がわかるようなポーズを取り入れることがおすすめです。
例えば、兄弟姉妹がいる場合は、身長順に並んだり、電車ごっこのように手をつないだりするポーズは、年齢と共に変化していく様子を後で見返したときに、成長を実感させてくれます。
また、お子様がパパやママに抱っこされているポーズも、大きくなるにつれて難しくなるので、今のうちに残しておきたい貴重な一枚となるでしょう。
家族写真として、皆で椅子に座ったり、床に座ったりするポーズも、家族構成の変化や成長を記録できます。
小物で個性を出す
撮影に使う小物は、写真に彩りやオリジナリティを加え、お子様の個性を引き出すのに役立ちます。
洋装には、ベレー帽やメガネ、おしゃれなブーケなどがよく似合います。
カラフルな紙風船は、お子様が遊びながら撮影できるので、自然な笑顔を引き出しやすく、写真も明るい雰囲気になります。
また、数字の「753」のブロックを手に持たせることで、七五三らしい記念写真になります。
紙吹雪(コンフェッティ)を効果的に使うことで、写真に華やかさと楽しさをプラスすることができます。
小物を上手に活用することで、より印象的で記憶に残る一枚となるでしょう。

まとめ
七五三の洋装撮影は、お子様の愛らしい姿や、家族の温かい絆を写真に残す素晴らしい機会です。
一人写しの可愛いポーズから、家族で楽しむ賑やかなポーズ、そして動きを活かした躍動感あふれるポーズまで、様々な表現が可能です。
撮影を成功させるためには、お子様の自然な表情を引き出すための声かけや、成長の記録となるポーズ選び、そして小物を活用した個性的な演出が大切になります。
今回ご紹介したポーズやコツを参考に、ぜひお子様にとっても、ご家族にとっても、一生の宝物となるような素敵な記念写真を残してください。