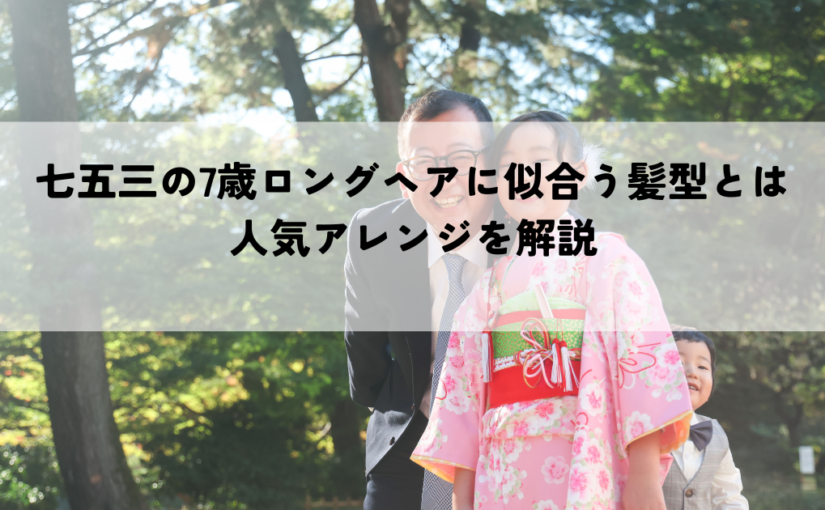七五三は、お子さんの健やかな成長を祝う大切な記念日です。
特に7歳のお祝いは、華やかな着物姿が映える特別な機会となります。
ロングヘアのお子さんなら、その豊かな髪を活かして、さらに特別なヘアスタイルを楽しむことができます。
一生の思い出に残る一日を彩る、素敵な髪型選びのヒントをお届けします。
七五三7歳ロングヘアの髪型
ロングヘアのお子さんが七五三で楽しめる髪型は、その長さとボリュームを活かしたものが豊富にあります。
可愛らしさや上品さを引き出すスタイルをいくつかご紹介します。
アップスタイル人気
ロングヘアをすっきりとまとめたい場合に人気なのがアップスタイルです。
編み込みやくるりんぱなどを組み合わせることで、立体感のある華やかなスタイルが完成します。
トップやサイドにボリュームを持たせたり、後頭部にふんわりとまとめたりと、様々な表情が楽しめます。
編み込みアレンジ
ロングヘアの魅力を最大限に引き出す編み込みアレンジは、上品で可憐な印象を与えます。
サイドに流れるような編み込みや、アップスタイルのアクセントとして取り入れるなど、アレンジ次第で個性を表現できます。
サイド寄せスタイル
髪を片側に寄せてまとめるサイド寄せスタイルも、ロングヘアならではの優雅さを演出できます。
ふんわりと巻いた毛先をサイドに流したり、ハーフアップにして残りの髪をサイドになでつけたりすることで、大人っぽい雰囲気に仕上がります。

七五三ロングヘアの髪型アレンジ
ロングヘアを活かしたアレンジは、さらに個性的で華やかなスタイルを作り出します。
飾りとの組み合わせで、より一層特別な雰囲気を演出しましょう。
リボン髪飾りで華やかに
ロングヘアは、リボンや和柄の髪飾りとの相性も抜群です。
アップスタイルや編み込みの結び目にリボンをあしらったり、サイドに大きめの飾りをつけたりすることで、一気に華やかさが増します。
お子さんの可愛らしさを引き立てる、特別な日のためのアクセントになります。
ポニーテールツインテール
元気で可愛らしい印象にしたいなら、ポニーテールやツインテールもおすすめです。
ロングヘアなら、毛先までしっかりカールをつけたり、くるんと巻いたりすることで、動きのあるスタイルが作れます。
トップにボリュームを出したり、編み込みを加えたりと、アレンジ次第で上品さもプラスできます。
ダウンヘアを活かす
ロングヘアをそのまま活かしたダウンスタイルも、エレガントで清楚な印象を与えます。
全体をゆるく巻いて自然な動きを出したり、ハーフアップにして顔周りをすっきりと見せたりするのも素敵です。

まとめ
7歳のお子さんのロングヘアは、アップスタイル、編み込み、サイド寄せ、ポニーテール、ツインテール、そしてダウンスタイルまで、多彩なアレンジが可能です。
リボンなどの髪飾りを上手に取り入れることで、さらに特別な日の装いを華やかに演出できます。
お子さんの個性や着物に合わせた髪型を選ぶことで、一生の思い出に残る素敵な七五三となるでしょう。